前回は「ゾイドを作ろう 3〜モーターの仕組みの実感と理解・「なぜ?」を考えながら作成・作成途中でモーターを動かす・動きの理解〜」の話でした。
作りながら色々な角度から見る:仕組みの理解

組み上がってきて、大体の形ができてきました。
 子ども
子ども出来て
きたね。



色々な角度から
見てみよう。



うん。
こんな感じ?


これから、頭・手・足などのパーツを組み立ててゆきます。
子どもは、



早く作って、
遊びたい!
こう思っていると思いますが、折角だから「仕組み」を理解してもらいましょう。



このオレンジ・黒の棒に、
これから手・足を取り付けるよ。



ふ〜ん。
なぜ、ここに棒があるんだろうね。
この棒が「軸」となって、足や手が動きます。


2箇所にはめ込むパーツ:どちらを先に入れるか考える


最初に作成したゾイドの「心臓部」とも言えるモーターのパーツ。
モーターは、一箇所でグルグル回ります。
その「回る部分」に様々なギアがついていて、様々なパーツが動きます。


手・足のパーツを組み立ててゆきます。



これは
こうかな?
パーツを穴に差し込むのは、一箇所だと比較的簡単です。
差し込み口が二箇所になると、立体的に組み上げることになるので、少し難しくなります。



先に
こちらを入れて・・・



次に、こっちを
入れるようにしよう。
「パチン」と二箇所の穴にはまりました。



よしっ、
出来た。



上手く
出来たね。
慣れるとすぐに出来る、この「二箇所にはめる」パーツ。
最初は、「どことどこに入るか」をしっかり把握することが大事です。
そして「一度に二箇所に入れる」のではなく、「一箇所を入れてから、二箇所目」を入れると良いです。
二つの図形や点が動く時:少しずつ分けて考える
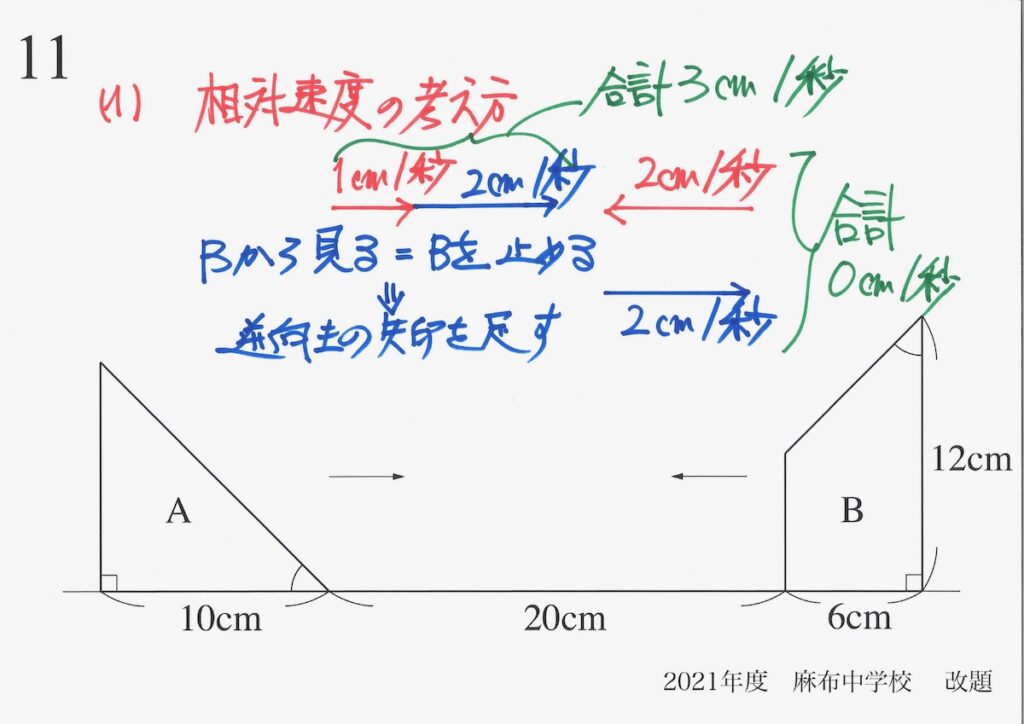

「二つの図形・点が動く」問題の解き方を、上記リンクでご紹介しています。
「一度にまとめて考える」と難しくなります。
「少しずつ分けて考える」のも良いですし、「変わらないモノに着目」するのが良いでしょう。
そして、相対的位置を考えるとわかりやすくなります。
ゾイドを作る時に「一度に二箇所」ではなく、「一つずつ」も共通する考え方です。


少しずつパーツが組み上がってきました。
このゾイドのように、「一つのモーターが様々なギアと関わって、全体が動く」のは面白いです。
身近な車や電車なども、同じような仕組みになっています。
算数や理科は、「基礎をしっかり固めて、応用力をつける」のが最も本質的で、学力が上がります。
そして、「一つのモーターが・・・」と同じように、



この考え方は
しっかり理解した!
「一題解くと、色々な問題が解ける」のが理想だと思います。
次回は上記リンクです。



