前回は「「現代のスパルタ教育」と「のびのび教育の反対」〜中高の教育方針・成績順位の公表の是非・学びへの意欲の刺激と競争心〜」の話でした。
急速な復興と高度成長と教育現場:高度成長で「失ったもの」
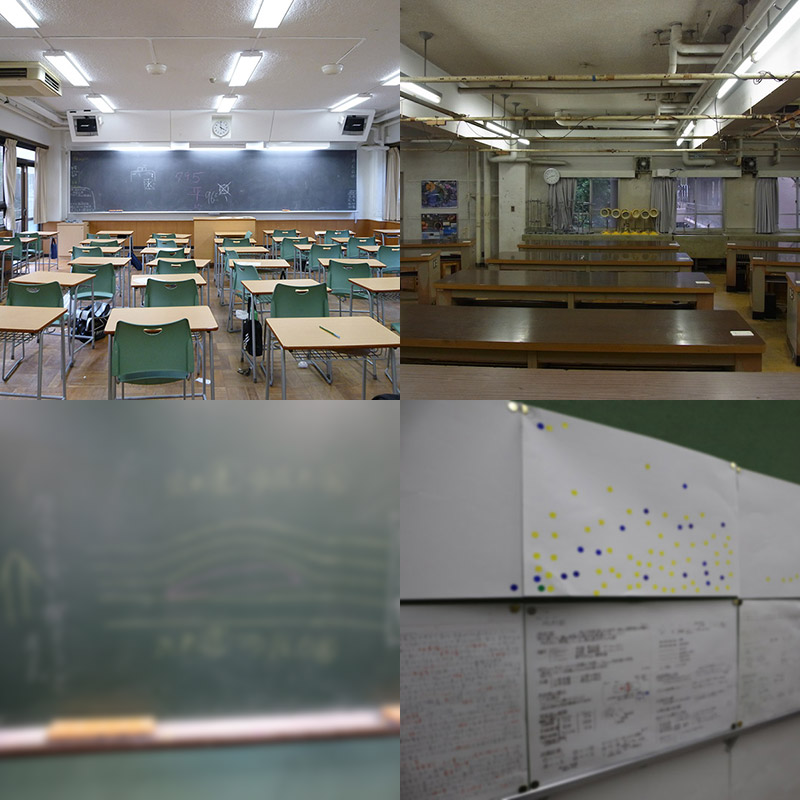
現代日本では、小学校から中学までは義務教育であり、高校以上は自由です。
この教育制度は、戦後に米軍による「大日本帝国から日本へ」の大改革の一つでした。
戦前の大日本帝国における教育制度は、現代とはだいぶ異なるものでした。
 文部科学省
文部科学省小学校から中学校における
義務教育の方針は・・・



私たちが策定する
学習指導要領に従ってください・・・
義務教育においては、文科省策定の学習指導要領があり、主に公立はこれに従って教育を進めます。
学習指導要領に関しては、賛否両論あります。
一方で、「要領」や「指針」などの「一つの基軸」がないことには国家の政策は進めようがなく、



まずは、学習指導要領に
準拠した教育を、しっかり行うこと!
学習指導要領は戦後に様々揺れ動き、近年では「ゆとり教育」の採用と停止が最も話題になりました。
「ゆとり教育」に関しては、別の機会に詳しく考えたいと思いますが、きっかけは高度成長期でした。


第二次世界大戦で敗戦した大日本帝国は、主に米国によって焦土と化しました。
そして、国中が荒廃の極みとなりました。



我が
大日本帝国は・・・
「大日本帝国」という、仰々しい名前だった国家名は、
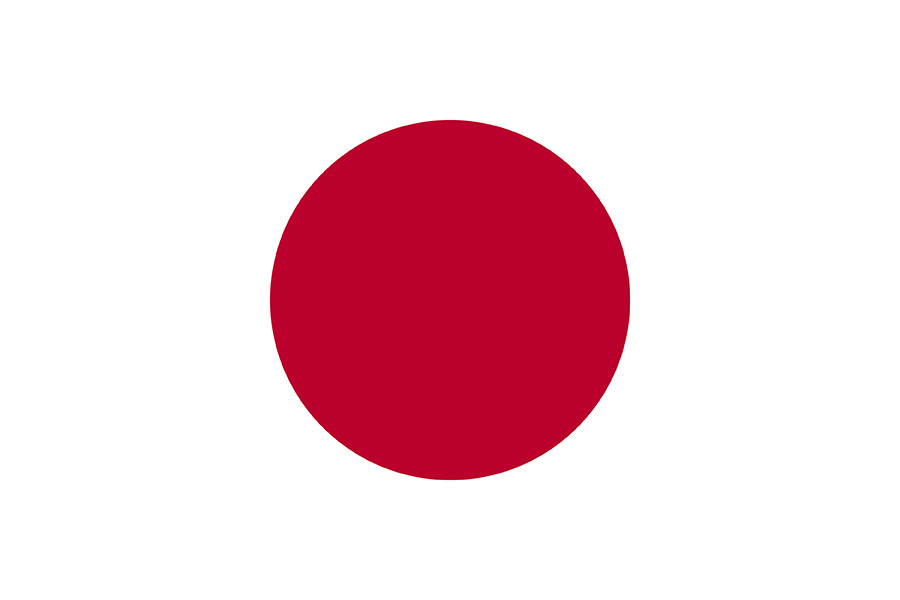
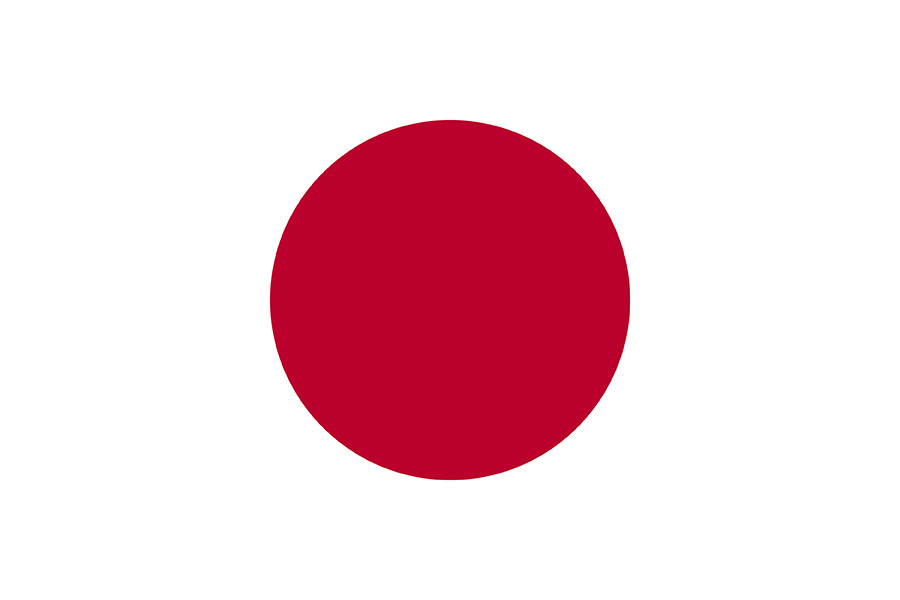

今日から、「日本」
という名前に変わります!
一気に「日本」に変わりました。
国家の根幹である憲法もまた「変わった」というよりも、米国によって「強制的に変えられた」のでした。
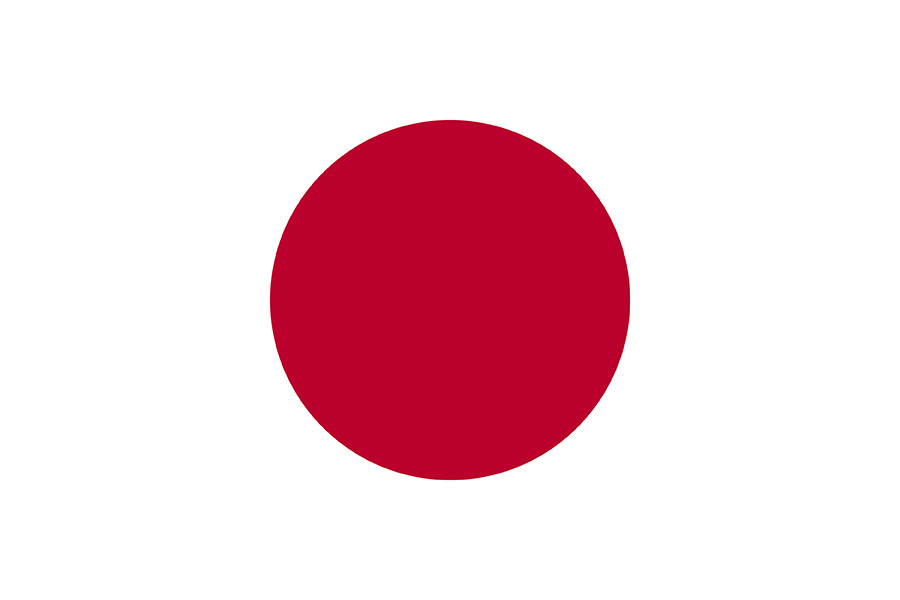
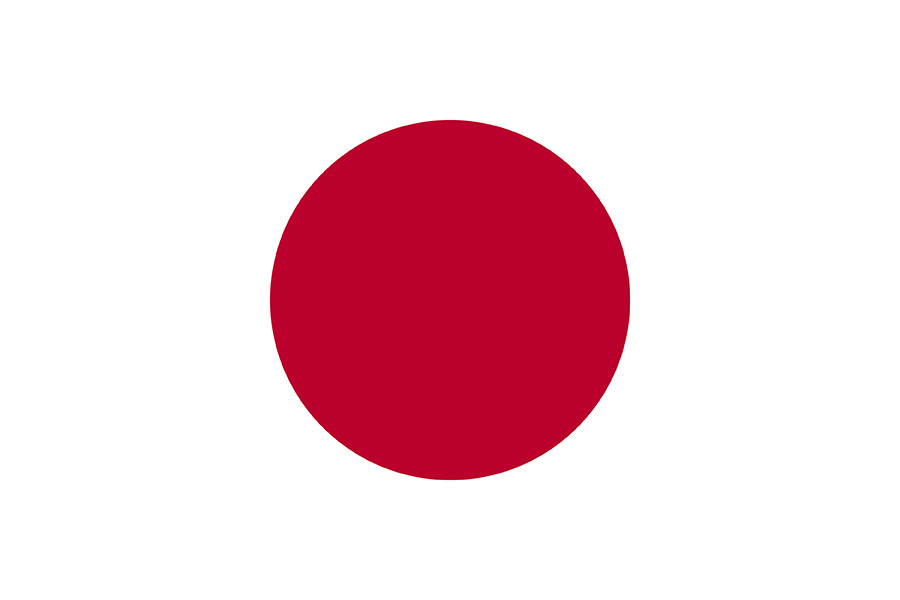

大日本帝国憲法を
廃止して、日本国憲法を施行します!
そして、「大日本帝国憲法から日本国憲法」になりました。
日本国憲法と大日本帝国憲法の違いの話を、上記リンクでご紹介しています。


その後、官民一体となって、日本国民全員が全力投球して、復興を果たしました。
おそらく、1945年から1970年頃までの日本人は、子どもから大人まで本当に一生懸命だったのでしょう。
大阪万博1970や高度成長期に関する話を、上記リンクでご紹介しています。
高度成長を遂げた日本人は、心や余裕が出来て、生活にゆとりが生まれ、自信がつきました。
戦後の日本人にとって、良い面が沢山あった高度成長期。
ところが、物事は「良い面」の裏側には、必ず「悪い面」があります。
そして、高度成長のプロセスにおいて、日本人が「失ったもの」もいくつかありました。
その結果、教育の現場では、校内暴力、いじめ、不登校などが社会問題になりました。
「詰め込み教育」と「ゆとり教育」の本質的方向性の違い


国家全体が荒廃した大日本帝国は、日本に変身して、猛烈な急成長を遂げました。
この急成長の最大の原動力は、「日本人の頑張り」ですが、



Japaneseと戦争したが、
二度と彼らとは戦争したくないな・・・



Kamikazeは信じられない攻撃で、
異常な民族だ・・・



まあ、戦争も終わったし、ソ連や共産主義との
対決のために、Japanの復興に力を貸そう・・・
日米安全保障条約などで、米国が日本を「事実上保護下に置いた」ような状況の中、復興したのが現実です。
急速な復興から高度成長は、当時の日本人にとっては極めて喜ばしいことで、



今度、
カラーテレビを買うぞ!



本当?
嬉しいな!
各家庭には、1950年代後半から電化製品の「三種の神器」がもてはやされました。
・白黒テレビ(1960年代からはカラーテレビ)
・電気冷蔵庫
・電気洗濯機
これらの電化製品や新幹線などの科学技術の根底には、旧日本陸海軍の軍部の技術の影響もありました。
何事も「急激な変化」は良くなく、1960年代〜1980年代の日本では、「置き忘れたもの」もありました。
人が集まるところには、必ずいじめなどが存在しますが、1970〜1980年の教育の現場はかなり荒れました。
筆者は、1980年代後半に公立小学校に通う小学生でしたが、ある時、同級生から、



なんか、僕たちの
学区のO公立中学の話聞いたんだけどさ・・・



学校のトイレに
タバコが散乱していたらしいよ・・・
公立中学のトイレに「タバコが散乱」と言う話を聞きました。
当時通っていた小学校で、この話を聞いた筆者は、



トイレでタバコ・・・
ちょっと嫌だな・・・
もともと筆者はタバコが嫌いなこともあり、「中学校にタバコが普通にある」状況に驚きました。



あとさ、結構中学生同士で
暴力とかも多いらしいよ・・・
さらに、校内暴力の実態なども聞いたこともありました。



学校で暴力?
絶対嫌だな・・・
現代と違って、ネットもスマホもない時代は、「伝聞の影響力」が現代よりはるかに強かった時代です。
そのため、これらの「公立中学校の教育現場における伝聞」の信憑性に関しては、確たることは不明です。
一方で「火のないところに煙は立たず」であり、「似たような話」は当時に「現実にあった」と考えます。
この話を聞いた小学生の筆者は、



中学受験頑張って、
私立に行きたい!
「タバコと暴力」の公立中学に対する忌避感から、中学受験を頑張る気持ちになったことを覚えています。



これはまずい・・・
詰め込み式の教育が悪いのか・・・
教育の場からの声もあり、文部省(文部科学省)は、「詰め込み教育」を否定する方針を固めました。
そして、1990年代に一斉を風靡したのが「ゆとり教育」でした。
これは、「詰め込み教育」の対極を行くものでした。



勉強しすぎると、心が
荒廃するから、勉強量を大幅カット!



自主性重んじる「調べ学習」を
導入して、思考力をつける学びを!
「ゆとり教育」の結果、学力の大幅ダウンが指摘され、「ゆとり教育」に急ブレーキがかかりました。
ここで、問題となったのは、「対極を一気に行ったこと」だったと考えます。
教育方針を「180度転換」とまで行かなくとも「150度くらい転換」したこと。
この「急激過ぎる方向転換」は、極めて大きな軋轢を生んだのでした。
ここにおいて、「詰め込み教育」と「ゆとり教育」の「本質的方向性の違い」が議論されるべきでした。
ところが、「ゆとり教育」からの揺り戻しによって、元に戻っているのが現状と考えます。
「ゆとり教育」にも良い面はあったはずで、「両立を図る」ことを推進すべきであったと考えます。



