前回は「着実に得点を上げる姿勢〜問題がうまく解けない時・初めてみる問題・実験して「状況を把握」する・自分が解く問題をうまく選ぶ・問題文全体を見渡す姿勢〜」の話でした。
難しく感じる算数の難問:センスや頭の良さは「ほぼ無関係」
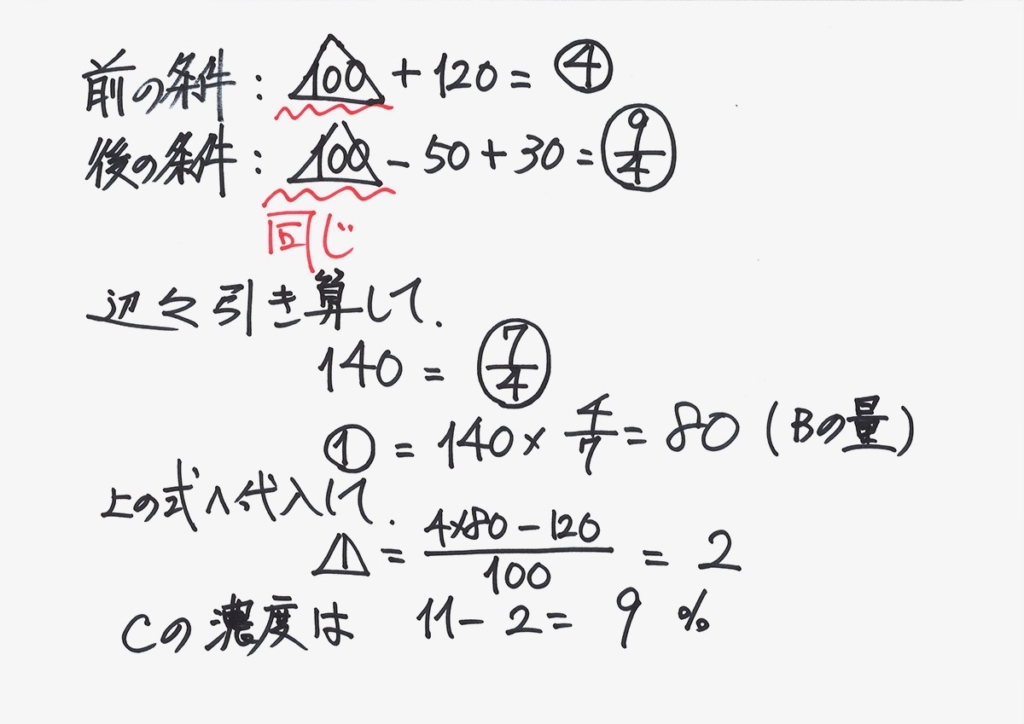
今回は、「算数が苦手」に感じている小学校6年生、5年生を対象とした話です。
 男子小学生
男子小学生算数って、
なんだか難しい・・・



私も算数は
ちょっと苦手で・・・
様々な科目を受験する中学受験生は、基本的に算数・国語・理科・社会の試験を受ける必要があります。
そして、これら「四科目」の中で、苦手意識が最も多い科目は算数です。



同じクラスで、
すごく算数出来る人いるけど・・・



ああいう人って、
きっと頭がいいんだろうな・・・
中学受験を目指す人は主に塾で、目指さない人も小学校のテストで、高学年になると差が出てきます。
小学校5年生くらいになると、どの科目でも「自分の成績」が明確になってきます。



国語で間違えた
問題多いけど・・・



そっか、この問題は
ここを答えれば良かったんだ・・・
国語・理科・社会ならば、なんとか挽回できそうな気もします。
一方で、特に中学受験の算数の応用問題は、「大人でも難しい」問題が多く、



算数は基本問題なら
ある程度出来るけど・・・



応用問題は
とっても難しくて・・・
算数は「挽回するのが難しい」ように感じてしまう方が多いでしょう。



こういう難しい問題が
解けないと、合格は難しいから頑張るけど・・・



どうやったら出来るように
なるのかな・・・
筆者は、小学校4年生の12月から、四谷大塚の日曜教室に通い始めました。
しばらく「日曜日だけが塾」でしたが、受験を一年後に控えた小学校5年生の2月から、



今日から土曜日も
塾で、週に二日塾だ!
「週に二日が塾」となり、当時「遅めのスタート」でした。
中学三年生くらいから数学が得意になった筆者ですが、中学受験の算数では、



どうやったら、こんな
難しい問題解けるんだろう・・・
多くの方同様、小学生の筆者も「算数の難問が解けない」ことに苦しんだ記憶があります。



やっぱり、算数が出来る人は
頭が良いのかな・・・
他の科目に比べて「頭の良し悪し」に起因すると考えがちな、算数の学力。
例えば、模試を受けた後に、他の科目で「出来なかった問題」に対しては、



あ、そうか、
この問題は、こうだったんだ・・・
「こういう答えだったんだ」で済みますが、算数で「出来なかった問題」に対しては、



あ〜、この問題は
こう考えれば出来たんだ・・・
「こう考えれば出来た」のに「出来なかった」という「とても悔しい思い」になります。
「もう少しで」や「ちょっとした視点」で解けるのが難問です。



算数はセンスが
必要なのかな・・・
実は、算数が出来る・出来ないは、センスや頭の良さとは「ほぼ無関係」です。
ここで「ほぼ」としたのは、センスが良い極めて少数の方が「得意」な可能性があるからです。
「算数が苦手」な人が「出来る」ようになる勉強法:描いて状況理解
ms15_01sts
今回は、上の問題の「解き方」よりも「取り組み方」「考え方」の話です。
この問題の解き方は、上記リンクでご紹介しています。
筆者が問題を追加しており、この問題は、入試問題としては「難問」と考えます。
算数の基本問題は、「問われていることが明確で単純」であることが多いです。
そして、この問題に限らず、応用問題は最初に様々な設定があって、



A君の歩く速さは
毎分何mですか?



A君とB君が
出会ったのは、何分後ですか?
色々なことが問われる形式が、ほとんどです。。
ここで、算数に苦手意識を持っている人は、



う〜ん、
何がポイントなんだろう?
う〜ん、と「問題文とにらめっこ」して、一生懸命考える人が多いです。
何度かご紹介していますが、算数の難問を解く際に大事なことは「状況を把握する」ことです。
そして、「状況を把握する」には「文章で表現されていること」を「自分なりに表現」するが大事です。
ms15_101ts
この問題の場合、まずは「駅と博覧会場」を描いて、その経路の道を線で表現します。
ここで、「駅」や「博覧会場」と書くのが「時間がかかる」ならば、「え」や「は」で良いです。



これは描かなくても
分かるから大丈夫だよ!
算数の難問が解ける人は、必ずこういう絵を描いています。



描かなくても、文章に
書いてあるから分かるけど・・・



どうやったら、A君の速さが
分かるんだろう・・・
この「文章→絵」にするプロセスでは、多少の時間がかかります。



テストでは、
時間がかかる、のは困る・・・
少しでも時間が欲しいテストでは、誰でも「素早く解きたい」はずです。
ここで大事なことは、「文章→絵」にするプロセスが「解く一部」であることです。
そして、この「文章→絵」にするプロセスにおいて、自分なりにポイントを解釈していることが大事です。
ms15_102ts
速さの問題では、本問のように直線状であるか、「池の周り」のようにグルッと回るタイプがあります。
これらの違いも「読めば分かる」のですが、実際に描いてみることが大事です。
ここでは、駅と博覧会場を描いて、A君とB君の速さを矢印で表現しました。
矢印の話を、上記リンクでご紹介しています。
矢印は、算数や理科では、とても分かりやすいので、ぜひ使ってみると良いでしょう。
矢印の向き:歩く方向や力がかかる向き
矢印の大きさ:歩く速さ(大きさ)や力の大きさ
矢印には「向き」と「大きさ」があって、それぞれが直感的で分かりやすいです。
ms15_103ts
上のように「動く歩道の速さ」を「A君の足元」に矢印で描きました。
「動く歩道の位置」を意識してこう描きましたが、「A君の速さにつなげて描く」も良いでしょう。
このように、文章題などでは「状況は自分なりに解釈して描く」ことが大事な一歩です。
そして、「状況をしっかりイメージする」ことが、極めて重要です。
問題が解けない人は、問題の内容が「しっかりイメージ出来ていない」ことが多いです。



確かに、こうやって
まとめたら分かりやすいかも・・・



文章と同じことだけど、
描いていると、理解した感じ・・・
・まずは、自分なりに文章内の状況を描く
・描くプロセスにおいて、矢印などを利用して状況の理解を深める
応用問題に苦手意識を持つ方は、ぜひ「描いて状況理解」を最初の一歩にしてみましょう。
次回は上記リンクです。



